今回は「離婚を迷われている人へ。まず知ってほしいこと」をお読みになられた方で、離婚の決意を固めつつある方に、
離婚をするなら決めなければいけない事をまとめてみます。
残念ながら、離婚をすることは簡単なことではなく、時間とエネルギーが必要です。
今まで二人で築いてきたものを分けるために、いろいろな事を考えなくてはいけません。
離婚後の姓と戸籍

離婚するとは、結婚の時に一緒になった夫婦の戸籍を別々にするということです。
結婚した時に1つになった戸籍で、筆頭者の戸籍に変化はありませんが、
筆頭者でない方は、その戸籍から離れて、下記の2択で選択する事になります。
・ もとの戸籍(親の戸籍)にもどる
・ 新しい戸籍をつくる
「もとの戸籍にもどる」場合、必然的に親の姓(旧姓)になります。
「新しい戸籍をつくる」場合でも、旧姓にもどす事ができます。結婚した時の姓のままにする事もできます。
戸籍から抜ける方は、旧姓にもどるのが原則とされているのですが、
結婚した時の姓のままにしたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を出さなければなりません。
離婚してから 3ヵ月以内です。
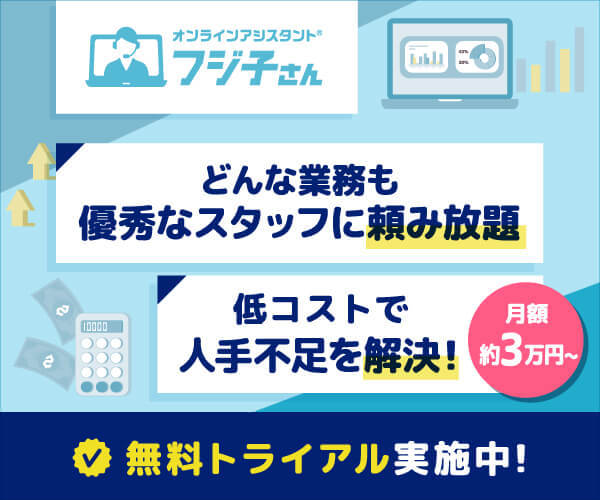
子供の姓と戸籍

基本的に、子どもの姓と戸籍は、親が離婚しても変わることはありません。
筆頭者と同じ姓と戸籍のままとなります。
【子供の姓】
筆頭者でない方の親が旧姓に戻すから、子どもの姓も同じにしたいと思うのは分かりますが、
何より子どもの気持ちを尊重し、変える場合は、進学のタイミングにするなど配慮が大切です。
子どもの姓を変える事について、期限はありませんのでゆっくり考えましょう。
15歳未満の子どもの姓の変更は、親権者が法定代理人として申立てできますが、
15歳以上の子どもについては、子どもが自分の意思で氏の変更を申立てることができます。
【子供の戸籍】
親が離婚後は、筆頭者と同じそのままの戸籍にとどまります。戸籍上の変化はありません。
もしも、筆頭者でない別戸籍になった方が、子どもを同じ戸籍に入れたい場合は、
子どもの住所地の家庭裁判所に、「子の氏の変更許可申立書」を提出します。
これが認められたら、「許可審判書」が申立者に交付されます。
申立者はこれを持って、最寄りの市区町村役場に「入籍届」を提出します。
この手続きにより、子どもは同じ戸籍に入り、同じ姓を名乗ることができます。
子供の親権

親権に含まれる意味としては下記のとおりです。
・子の身上監護権、およびその義務
・子の財産管理権、およびその義務
これらに加え、子どもが何か契約をする場合の法定代理人としての立場も含まれます。
夫婦の協議によって決める事ですが、未成年の子どもは母親が親権をもつ事の方が多いようです。
しかし、親権者にならなくても、「子どもを扶養する義務」は 継続的に続きます。
また、「子どもと面会する権利」「財産を子どもに相続させる権利」も あります。
子どもにとってはどちらも親であり、両親の離婚によって子どもに不利益が生じないよう、親は真剣に考えなくてはなりません。

養育費

養育費は子どものためのお金です。
本来、子ども自身に請求権があるので、子どもを育てている親が、元配偶者から養育費を受け取らない約束をしたとしても、子どもの請求権は失われません。
財産分与や慰謝料と、養育費はまったく別の問題なのです。
【養育費の対象となる費用】
・衣食住の経費
・教育費(塾などを含む学費など)
・医療費
・娯楽費
・おこづかい
・交通費
・その他(ベビーシッターなどの費用)
養育費は、子どもが社会人として自立するまで必要なすべての費用です。
どちらが再婚しても、養育費の負担義務は変わりません。
【養育費の金額】
金額については、各家庭の事情により違いますが、養育費の参考資料として、裁判所では、
2003年の「判例タイムズ」1111号で、ガイドラインとしての算定表(早見表)を公表しています。
夫婦二人の年収がたて軸・よこ軸で表示されていて、交わるゾーンの金額が養育費の目安(月額)となっています。
これをもとに、しっかりと話し合いましょう。
財産分与

まず、財産分与の対象とならない物があります。
・結婚前に貯めた預貯金・有価証券など
・結婚前に取得した家具など
・結婚後でも、親兄弟から贈与された物や相続した遺産など
それら以外の、共有の財産(預貯金・不動産・家財道具など)すべてを合わせて、分けます。
結婚後に夫婦で協力して築いてきた財産のうち、どちらか一方の名義のものでも分与対象です。
マイホームなどの不動産がある場合は、売却して現金で分ける方法と、どちらかに譲渡して住み続ける方法があります。
売却してローンが返済できれば残額を分ければいいのですが、できない場合には複雑になります。
どちらかが住み続けることになり、ローン残高が売却価格を上回る場合は、手放す配偶者に時価評価とローン残高の差額に対する分与率分を現金で支払うことになります。
離婚後の生活を考えたうえで結論を出すことが必要です。
賃貸の場合は、返還される敷金も分けることになります。
その他、自動車や株、美術品などは、すべて売却して現金化して分けることがキレイですが、
売却しない場合はその時の時価で、所有する方がしない方に分与率分払うという事になります。
話し合いに合意できたら
強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しましょう。
話し合いで金額の合意ができても、この公正証書を作成していなければ、養育費の支払いが滞った時に、地方裁判所による強制執行で差し押さえを実行することができません。
ここがポイントで、取り決めた事をしっかりと文書で残すことが大切です。
お互いに納得できる金額に合意できない場合は、調停を申立てるべきでしょう。
その点、調停で話し合った事は調停調書で残され、公正証書と同じ効力を発揮するので便利です。
離婚した時から経済的な変化が大きく、養育費の増額や減額を求めたい時も、調停を申し立てることが出来ます。
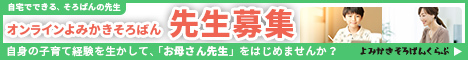
まとめ
いかがだったでしょうか。
私はこれらの財産を表にして、それぞれの価値を計算し、調停で話し合う材料にしました。
しかし、私が知っている財産を書くだけなので、もしも相手が私の知らないところで隠し財産をつくっていたら、その分は隠されたままになっていると思うし、私は損している訳です。
実際に、知らない間に株を始めており、私が知ったもの以外でも黙っているものがありました。
多分それ以外にもあっただろうと思います。
離婚となると、最後のこのお金の問題がもめる原因となる事が多いでしょう。
でも、思う事は、お金には代えられない価値のあるものがあり、出し惜しみすることなく、気持ちよく別れられたらいいなと思います。
お互いに今後の人生が豊かになるように…





